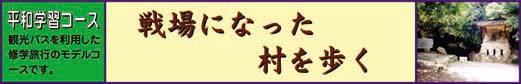■コースの説明
戦争は一瞬にして、それまでに築き上げてきた文化を破壊してしまいます。さらに、多くの人々の生命も奪ってしまいます。昨年、世界遺産登録された座喜味城跡も戦争の砲火で破壊され、復元には長い年月と多大な費用が必要だったのです。
読谷村は米軍の沖縄本島上陸地点になりました。疎開しなかった村民は、ガマと呼ばれる自然の鍾乳洞窟などに潜んでいました。シムクガマでは約1,000人が米軍の投降呼びかけに応じて無事に保護されましたが、翌日、同じ波平のチビチリガマで83人の村民が「集団死」をとげました。
このコースは戦場の村を歩いて、沖縄戦の実相にふれる基本的な平和学習コースです。 |