座喜味城跡
座喜味城跡は15世紀の初頭、築城家としても名高い読谷山按司護佐丸によって築かれたといわれています。護佐丸は当初、座喜味の北東約4kmにある山田グスクに居城していましたが、1416年(1422年の説もあり)中山尚巴志の北山城(今帰仁城)攻略に参戦し、その直後、地の利を考慮し座喜味へ築城したといわれます。
1943年、日本軍の読谷山(北)飛行場建設にともない、いち早くここに目がつけられ、翌年8月、第21野戦高射砲司令部指揮下の独立高射砲第27大隊第3中隊(光本中尉中隊長)によって陣地構築が進められました。完成した高射砲陣地は、十・十空襲の際には応戦はしたけれども効果を発揮することは出来なかったということです。もともと高射砲とは読んで字のとおり、高空を飛行する航空機を撃つもので、低空で襲ってくるアメリカ軍の艦載機に対して下向きに発射できず、逆に攻撃を受けてしまいました。
戦後、1956年に琉球政府の重要文化財に指定され、日本復帰の1972年には国指定史跡となります。翌年の1973年から1985年の間、文化庁・沖縄県の補助を受けて城跡の発掘調査や城壁修理が進められ、日常的に歴史と触れあえる空間としてよみがえりました。 2000年12月2日には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の資産のひとつとして世界遺産に登録されました。
|
<問い合わせ先>
読谷村立歴史民俗資料館
住所:読谷村座喜味2975
TEL:098-958-3141
<見学時間の目安>
30分
<駐車場>
無料駐車場有り(40台) |
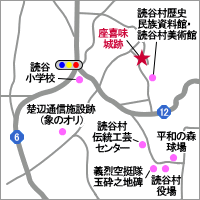 |
|
座喜味城跡1  |
座喜味城跡2  |
| 









